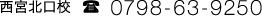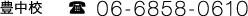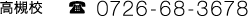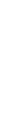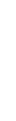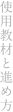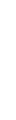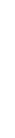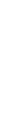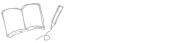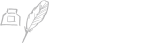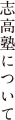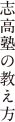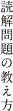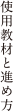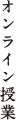2か月前に始めた社員のブログ。それには主に2つの目的がありました。1つ目は、単純に文章力を上げること。そして、2つ目が社員それぞれの人となりを感じてとっていただくこと。それらは『志高く』と同様です。これまでXで投稿していたものをHPに掲載することにしました。このタイミングでタイトルを付けることになったこともあり、それにまつわる説明を以下で行ないます。
先の一文を読み、「行います」ではないのか、となった方もおられるかもしれませんが、「行ないます」も誤りではないのです。それと同様に、「おなじく」にも、「同じく」だけではなく「同く」も無いだろうかと淡い期待を抱いて調べたもののあっさりと打ち砕かれてしまいました。そのようなものが存在すれば韻を踏めることに加えて、字面にも統一感が出るからです。そして決めました。『志同く』とし、「こころざしおなじく」と読んでいただくことを。
「同じ」という言葉を用いていますが、「まったく同じ」ではありません。むしろ、「まったく同じ」であって欲しくはないのです。航海に例えると、船長である私は、目的地を明確に示さなければなりません。それを踏まえて船員たちはそれぞれの役割を果たすことになるのですが、想定外の事態が発生することがあります。そういうときに、臨機応変に対処できる船員たちであって欲しいというのが私の願いです。それが乗客である生徒や生徒の親御様を目的地まで心地良く運ぶことにつながるからです。『志同く』を通して、彼らが人間的に成長して行ってくれることを期待しています。
2023年12月
2025.01.10vol.45 ○妙の境目(竹内)
2025年最初の「志同く」。本年もよろしくお願いいたします。
高2の生徒が意見作文に取り組んでいた際に、「嫌いであることの理由は言語化できるが、好きであるものの方がそれをするのは難しい」といったことを述べていた。この「嫌い」はやりたくないとか、できないとか、もう少し意味を広げられる。そういうことがあった時にはそれを正当化するための言い訳をぽんぽん出してしまいがちである。もちろん様々な事情でやれない、できないことというのは存在するが、そのような場合には理由を求められることが多い。好悪は感情の一つだからこそ、「嫌だから」で済ませるのでなく何かしら相手を納得させうるものが必要ということなのかもしれない。それに比べると、確かに「なぜ好きなのか」を明らかにしなければいけないことは少ない。そんなあまり考えていなかったことに目を向けさせるために、意見作文を通じてしっかり言語化させるところまでが、我々にできることである。
講師向けの第2回のワークショップを昨年の11月末に行った。夏の第1回目は読解問題を題材としており、今回は意見作文について扱った。授業で実際に使用しているテーマに対して各自作文し、文章そのものやその際に考えたことを共有することで指導する際の切り口を増やしてもらうことが狙いである。取り組んでもらったのは「自身の名前」についてで、生徒たちよりも長い人生経験のある講師たちの書き上げたものには「自分とどう向き合ってきたのか」が表れており、どれも読みごたえがあった。一人一人の講師がそのテーマをどのように解釈しているかを示していくことも、生徒とのやり取りをより活発なものにしていくためには欠かせない要素である。
さて、その名前に関していえば、「親から一字もらう」という付け方がある。父親が「康高」なら「康介」とか「康一」のように名付けるといったものだ。同じ文字を共有しているのは家族としての結びつきが感じられて素敵である。一方、竹内家は4人きょうだいなのだが、誰一人親からの漢字を譲り受けていない。さらにいえばきょうだい同士でも一文字も共通していない。顔も性格も「似ている」と言われることがあまりないのは、この名前も影響しているのかもしれない。ただ、全然違う、時には理解不能な存在が身近にいたことは私の物事の受け入れ能力をかなり高めてくれた。
末っ子長男の弟は今年度に30歳になる「大谷世代」であり、紛うことなき大人である。しかし、その大谷も実家に帰ればきっと一人のかわいい息子であるように(そうであってほしい)、彼と同い年である我が弟も家族からすれば変わらず心配ばかりが頭をよぎる存在である。中でも母にとっては、一人だけの息子のことが常に気がかりだった。弟は就職してすぐは関西に勤務していたものの、全国転勤の可能性がある職場だったので今は静岡で一人暮らしをしている。物理的にもそうだし、まめに連絡をよこすタイプではないので精神的にも距離ができてしまっており、特に去年一年は状況がよく掴めなかった。そんな中、母方の祖父が体調を崩したのだが、その連絡がなかなかタイムリーに進まない。温度差のあるやり取りは母を苦しめた。その時により強い怒りを抱いていたのは私の方だった。何なら怒りをぶつけない母にまで腹が立ったくらいである。しかし、それが母親というものなのだとも思った。
それから4か月ほど過ぎて、前回の文章で取り上げた『ぼくが生きてる、ふたつの世界』に出会った。前にも述べたが、聴覚障害のある両親のもとで生まれ育った一人の少年の苦しみや親への思いが描かれた作品である。著者自身が年を重ね、親元を離れ、仕事をし、新しい出会いをたくさん経たことで、親に対する理解の深まりや認識の変化が生まれていったという。こんなの、弟には絶対に触れさせたい。考えさせたい。著者が猛烈にそう思ったのと同じように、自分はアホやったと気付かせたい。めちゃくちゃにそう思った。でもきっと、映画なり小説なりの情報を送りつけたとて、きっと弟は見ないし読まない。そういうときにこっちの魂胆はすっけすけになっているのだろう。子どもに読ませたい本が必ずしも受けないのは、「こうなってほしい」が先行してしまっているのもあるはずだ。だから、自分で辿り着いてもらわないといけない。生徒に対しても、本選びをする際に明らかに「このレベルを読めるようになってほしい」ということを伝える場合もあれば、そこまで深い意図を持たずに進めることもあるし、何ならあえて手助けせずに何を手に取るかを見守る時もある。ある程度導いてあげる必要はもちろんあるが、意識的にそうしていると良いタイミングでいつもよりも挑戦的なものをチョイスできていることをよく目撃してきた。微妙な塩梅だけれども、絶妙に気をつけている。
年末になって、弟が実家に帰ってきて家のことをいろいろやってくれた。大みそかには久しぶりに長電話をした。もしかしたら作品に出合ったのかもしれないし、そうではないのかもしれない。
親御様に有益な情報を提供することが「志同く」の一つの目的であるとき、それができているのかというのを疑いながらいつも書き上げている。幸いなことに私の周りは家族をはじめ色々な人にあふれている。そんな彼らとのかかわりを通じて、私を伝えていきたい。