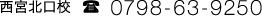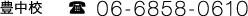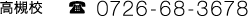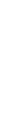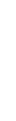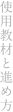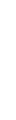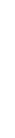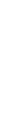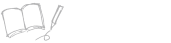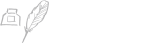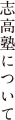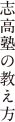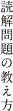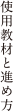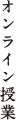2023.08.29Vol.605 目的を見つめ直すことで手に入れた本質的な差別化
体験授業に来られた親御様には、次のような説明をする。なお、ブログ用に少し付け加えていることなどもある。
『コボちゃん』、『ロダンのココロ』では、「つなぎ言葉+誰がどうした」といった単文(主語が一つの文)で書かせることを徹底させます。子供たちはつなぎ言葉や主語を感覚的に入れたり抜いたりするので必ず入れさせます。また、マンガの中の表現の使用と同じ言葉の繰り返しを禁止することで、使える言葉が増えるようにします。なお、志高塾における語彙とは、ただ知っている言葉ではなく、使える言葉、つまり、書ける、話せる言葉のことを指しています。「つなぎ言葉+誰がどうした」とすることで文章にリズムは無くなりますが、この段階では、まずはいろいろな表現を用いて、前後の文の関係を意識しながら論理的にまとめられるようにすることを大事にしています。
次に『きまぐれロボット』ですが、この教材は元々それまでのものと同様に200字で要約させていたのですが、要点を外す生徒が少なくなかったため、その前に我々が「メモ」と呼ぶプロセスを挟むことにしました。「要点とは何だろうか」ともう一人の社員と一緒に考えたときに、物語文においては、心情の変化とその理由を掴むことだという結論に達したからです。「メモ」において、「変化の前」、「変化の後」、「変化の理由」の3つをワンセットで押さえることで、話の骨格を捉えられるようになります。また、要約作文では、これまでのように「つなぎ言葉+誰がどうした」の制約は取り払います。つなぎ言葉や主語を入れるかどうか、単文にするのか複文にするのかの選択をした上で、短い文と長い文を混ぜながらリズム良く構成することを意識させます。そして、「メモ」、「要約作文」と来て、最後に取り掛かるのが、我々が「主題」と呼ぶものです。そこでは、失敗の原因(この短編集では、主人公が大抵何かしら失敗をするので)を抽象化し、そこで終わるのではなく、さらにどうすれば良かったのかまで考えさせます。たとえば、1話目の、「ある男が、博士が開発した寝る時に使うだけで英語が話せるようになる枕を喜んで借りたが、期待した成果が得られずに不満気に返しに来た」という話では、「何か身に付けたいことがあれば、人や物に頼らずに努力しなければならない」となります。ここで、「英語」や「枕」などの話の中の具体的な内容が入っていれば抽象化が不十分ということになります。この訓練をすることで、読んだ本の内容について尋ねたときなどに、「AがBしてCになった話」とただ具体的な事実を並べるだけではなく、「少年たちが、いろいろな楽しいことや苦しいことを共に経験していく中で成長していく話」といった感じで、話のテーマが意識できるようになって行きます。
そして、要約作文の最終教材である『小さな町の風景』についてです。これも『きまぐれロボット』と同様に200字の要約作文だけをさせていたのですが、表面を撫でたようなものになることが少なくなかったため、何かしら手を打つ必要がありました。当時、入塾するのは中学受験予定の小学3, 4年生の男の子が多く、第一志望は甲陽です、という親御様が少なくありませんでした。もう一人の社員と私は共に進学塾で働いた経験はなく、過去問事情に詳しくなかったものの、「甲陽の物語文の記述が難しいらしい」というのを体験授業の場などでも聞く機会が少なくありませんでした。そこで、甲陽の対策と『小さな町の風景』の課題解決の2つの目的のために、「要約作文」の前に60字の記述を2問解かせることにしました。そのために、二人で一緒に、甲陽の過去問を10年分ほど解いて、それに対応できるような問題を作りました。
開塾するにあたり、教材を含めたやり方などをそのまま盗むのは良くないというのが自分の中に強くあった。その理由は主に2つ。もし、同じことをするのであれば、わざわざ自分がする必要がない、というのが1点。そして、もう1つが、そのような工夫をしない人たちが教えること自体に問題があるのではないか、ということ。1点目に関しては、元々いた国語専門塾で「こうしてはどうでしょうか」といくつか提案をしても納得の行かない理由で受け入れなかったことが自分で始めるきっかけになったので、「自分ならこうする」というのはそれなりに持っていた。それだけではなく、できるだけオリジナルと呼べるものを増やすために、たとえば、4コマ漫画として『コボちゃん』を使うのではなく、『ののちゃん』にすることなども検討した。しかし、試行錯誤をした上で、結局は『コボちゃん』に落ち着いた。その過程で、別のものただ置き換えるだけでは本質的な差別化とは言えない、という当たり前のことに気づいた。
自己弁護をするわけではないが、このことに限らず、大事なのは、本質は外さないことではなく、外したとしてもきちんと本来あるべきところに着地できることなのだろう。大抵の場合、そのような失敗を犯す原因は本来の目的が見えなくなってしまうことにある。上の場合で言えば、「志高塾オリジナルと呼べるものを作りたい」という邪念が、「生徒を成長させるために何をすべきか」ということを覆い隠そうとしていたのだ。それを振り払えたときに、どのようにすれば目の前にある教材をより活用できるかという視点を持てるようになった。その結果、それぞれの教材で太字部のようなやり方を手に入れるにいたったのだ。気づけば、体験授業で親御様に「志高塾ではこうやって教えています」と説明していることは、自分たちで考え出した方法論が中心になっていた。
上で二度「もう一人の社員」という表現を用いた。その彼女がいなければ、志高塾を立ち上げるのはもう少し後になったかもしれないし、上のような方法論にたどり着くまでにもっと多くの時間を要したはずである。次回、その彼女が果たしてくれた役割について述べ、このシリーズを終わりにする予定である。